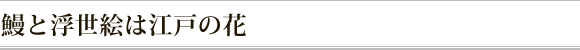土用丑の日に鰻を食べる
鰻を食べようというとき、ふつうは蒲焼きだろう。

豊国画(提供・松井 魁)
現代風の蒲焼きの始めは江戸時代で「土用丑の日に鰻を食べる」もやはり江戸時代で、これには諸説があって、真説は定かでない。
そこで真実性のあるように伝わっているのは次の説である。
大田蜀山人は平素か鰻が好きで、当時江戸時代の鰻屋の頼みで、店の繁盛方策を考えた。
「土用鰻は効果があり、特に丑の日の日には食当たりしないという意味のことを宣伝させた」 これが始まりだという説。
また一説に、当時有名な平賀源内が、鰻屋の依頼で看板を書いたときが、たまたま土用の丑の日だったので「本日土用の丑の日」と達筆で大書きして店頭に掲げたところ、有名人であり博学の先生が書いたものなのだから、人々は丑の日、鰻、栄養に深い意味があるものと考え、これが大評判となり、先客万来の大盛況。他の鰻屋も負け時と、これを真似るようになったと伝えられる説。
したがって決定的なものはないが、夏やせの妙薬としての鰻が、長い年月のうちにいろいろな伝承と結びつき、これを平賀源内か大田蜀山人か、または有名人の誰かがうまく宣伝に使って、大衆に受けたのでは ないかと思われます。この江戸時代は、ちょうど食道楽に贅をつくそうとする風潮もあったために、大評判となったのでしょう。
江戸文化の華は浮世絵

子供の鰻獲り 五渡亭國貞画
(提供・松井 魁)
江戸文化を語るとき、まず思い当るのが浮世絵である。
浮世絵には春画をはじめ役者画、美人画、魚づくし、風景画と、いずれも大衆が好みそうな絵柄を多くとりあげた。
当然ながら食文化の中心である鰻をテーマにした浮世絵もかなりある。それは川や沼での鰻とりの風景画であったりした。主な作家は、歌麿、北斎、広重、国芳などがあげられる。

外道浄る里づくし 一勇齋國芳画
(提供・松井 魁)

狸の川がり 一勇齋國芳画
(提供・松井 魁)

うちわ絵 朝櫻樓國芳画
(提供・松井 魁)

見たて五行かがり火 一勇齋國吉画
提供・松井魁

孝貞女鑑 玉蘭齋貞秀画
提供・松井魁

貞操千代の鑑 一勇齋國吉画
提供・松井魁

見たて五行かがり火 一勇齋國吉画
提供・松井魁

孝貞女鑑 玉蘭齋貞秀画
提供・松井魁
天保8年、登亭の前身「中市」創業
登亭といえば、蒲焼きの・・・・・と思われているが、鰻が食文化の中心であった江戸時代に、登亭の初代中野屋市太郎は天保年間に千住にて川魚問屋「中市」を創業した。
川魚問屋「中市」は、姓の「中」と名の「市」をとって呼称し、4代目田中市太郎(福太郎)に至るまで、歴代の当主は、先代より、田中市太郎を譲り受け、襲名してきたのである。
初代中野屋市太郎が生まれた当時(文化・文政)は、江戸の町から庶民の町になっていく歴史の大きな転換期である。
文化面でも、江戸の文化が充分に確立し、独特の色彩を持ったのも、この時代だといわれている。
既に述べた浮世絵の作家として、歌麿、北斎、広重、国芳などのそうそうたるメンバーが出てくるのが文化・文政時代であるし、浮世絵と並んで注目されていいものが、読本、つまり小説であり、本永春水や十辺舎一九の作品のように独特な色彩を出した小説が多く登場してきたのもこの時代であった。
もうひとつの特色は、当時の人々が江戸というひとつの地域にとらわれず、世界を見る目をだんだんと作り上げ、外国に対する芽が豊かになり、間宮海峡を発見した間宮林蔵や千葉で生まれて、江戸で生活した伊能忠敬は、測量の技術や蘭学を学んで、日本全国の地図を作っているのはよく知られていることだろう。
このような歴史上の有名な人物が登場する時代に生まれた先代市太郎は、天保8年に千住青果市場内の千住中組42番地(現在の千住河原町49番地)に「中市」を創業したのである。
江戸の北の玄関口にあるこの市場の起源については、明らかではないが、「天正年間(1573~91)に始められ、千住大橋がかけられると、野菜、川魚などの荷扱いが急にふえ、享保年間(1820年頃)には、神田、駒込の市場とともに江戸の三市場となり、幕府のご用市場となった」とある。
千住河原町にある鎮守河原稲荷神社境内には、明治39年建立の「千住市場開設三百三十年記念碑」があり、逆算してみると、天正4年(1576)になる。だが市場の形態となったのは、やはり江戸時代に入ってからのことだろう。
「新編武蔵風土記稿」によると「享保(1716~)の頃より毎朝市を立て、五穀野菜、あるいは川魚をひさぐもの日に盛んなり、故に明和中(1764~)より各問屋を立てて税をあつむ」とあるから、物資が大量に出回り、専門店相手の問屋が必要とされた江戸中期に、卸売市場として機能化したと見られる。
千住市場の一日は夜中から始まり、荷主(山方)は夜通しで千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城方面から荷車で午前2時頃に到着し、各問屋で仮眠する。午前4時頃に買主(仲買人)が集まると、各問屋の庭先で立ち会いを始める。当時立会いせりをおこなったのは千住だけだった。その他の市場は、みな相対取り引きの形式であり、また千住だけには、投師という出仲買人がいた。
彼らは、千住の問屋でいち早く仕入れた品物を、他の市場(駒込、神田、京橋、浜町)へ運び、その周辺にくる小売商に売りさばく商売をした。
いわば、中間搾取ともいえる利ざやをかせぐ人々である。これらの人々でおこなうせり声が、いせいよく「チャチャイ、チャチャイ」と聞こえたことから、千住市場のことを、チャチャバと呼ぶようになり、今も青果市場をチャチャバと呼ぶようになったわけである。
この市場には、荷主、問屋、仲買、投師の他に、買主の荷物を手押し車で運ぶ軽子とい人々でにぎわっていた。