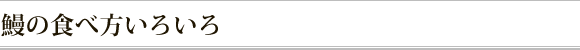蒲焼

鰻料理といえば蒲焼をすぐに思い出す。蒲焼は鰻の本当の味を見い出した、日本独特の代表的な料理法である。
しかし、お隣りの中国には、これに似た古い料理法があり「大観本草」(大観2・1108年)に椒醤炙方として記載されている。これはきわめて蒲焼に似た料理法である。しかし、現在の中国にはまったくない。
この蒲焼の起源については、いろいろな説があり、それら関連した文献は後述するとして、これらの説を大別してみる。
- かんばしい香りが早く人の鼻に入る意味で、香ばやが転じたとする説。
- 昔は長い丸のまま、たてに口から尾まで竹串に刺して、塩焼にしたが、その形が蒲の穂に似ているので、がまやきといったが、それが後に転訛したとする説。
- 鰻を焼いた時に色が、樺(かば)色だとか、樺皮に似ているから樺焼に転じたとする説。
- 椛(さくら)の皮をすいて、竹串のかわりに、はさんで焼く、椛の皮を、かばというからという説。
- 蒲鉾(かまぼこ)から転じたとする説。 これら5つの説で、第1説の香ばやという語源は、平安時代の後期、藤原明衡という学者の著書「新猿楽記」に、香疾(かばや)大根について、次のように記してある。
すなわち、香疾(かばや)大根という名見えたり、こはかうばしき香の疾く他の鼻に入の謂なるべければ鰻(うなぎ)の香疾はよく相当したる名なり、鰻を焼るほど香疾ものは又あるべからず。
つまり、この香疾(かばや)がのちに蒲焼にかわったとする説である。高田松屋は「松屋筆記」(1815年)に、この説を認めて、蒲焼と書くは誤りで、香疾焼の義としている。
第2の説について、燕石は「神代のなごり」(1836年)に次のように述べている。
蒲焼は昔は鰻の口より尾の方へ竹串を通して丸焼にしたること、今のイナ、コノシロなども魚田楽の如くにしたる由聞えたり(略)

彫刻家の故朝倉文夫氏が『うなぎ』という本に「鰻公(うなこう)」というタイトルの随筆を寄せられている(1954年)。
その一部分をご紹介してみると――『鰻料理の東京と上方との相違は誰でも知ってのとおりであるが、これが九州になると、又一種の料理方をやっていた記憶がある。鰻だけは他の料理と異り永久に地域的な風味を発揮して存在するのではあるまいか。
東京で上方風をやったり、上方で江戸前をやったりしても決して繁昌するものではあるまい。というのは、鰻は淡水魚といっても温水魚で地域的に気候風土の関係が多分に影響している。九州産は皮膚(かわはだ)が柔く、中国、大阪、名古屋、東京、仙台と北海道に近くなるほど皮膚がかたくなるわけで、この点から大阪あたりまでは所謂上方風料理方でないと風味を損することになる。
筆者は九州、鰻の産地として名高い大野川の辺りに生れたので、50年前東京ではじめて江戸前を丁戴して、こんな柔かなもの、何だか一度腐敗させて焼き直したのじゃないかと口に入れたものを嚥下するのを躊躇して大笑れしたことを思い出す。現在では蒸がどうだとか材料がバチだとか、いささか講釈じみたことをいっているが、ただしかし、鰻茶漬となるとお国振りを思い出す。(中略)
肉を3つ切にして2本の串にさし、臓もつは1本の串、一応焼いたものをタレに浸し又焼く又浸す又焼く、3度位繰り返して串を抜きタレの中に浸しておく。御飯の上にこれをのせて、充分お茶をかける。最初の半分位を呑み干して2度目のお茶で本味になる。これは50年前の田舎料理の記憶で現在果して如何なものかしかし2度目のお茶漬なら戴いてみたいような気もする。(後略)』

昔、蒲焼といひしは魚の口より尾にまで竹串を貫きたるが蒲の穂に似たる故に号したるなり。当世は蒲の穂には似もつかず鎧の袖に似たり。
第3説には、山東京伝「骨董集」(1813年)で反対しており、久松祐之は「近世事物考」(1848年)で同意見を述べている。
黒川玄逸「雍州府志」(1684年)に次のように述べている。 宇治川産の鰻を宇治丸と云って之を焼いたものは樺焼(かばやき)と謂(い)い、その色は紅黒くて恰度(ちょうど)樺皮に似ているからである。酢につけたものも格別によく遠く持参してもいたまないのが特徴だ。
第4説には、醍醐散人が「料理早指南」(1801年)で、次のように述べている。
椛(かば)やき――うなぎ、はも、さより、沖さより、ふかなどのるい長くきり小串にさしてやく事也。近来かばやきといふはうなぎより云ひ出たるやうに思ふなれども左にあらず。かばやきといふは、紀州よしの山のふもとにて椛(さくら)のかはをすきて竹のくしのかはりにかりにはさみてうる、その椛のかはをかばといへば、その形に似たるよりかばやきといふなり。しかれば何にても右のなりにしたるはすでにかばやきといひてからなり。
第5の説は、喜多村節信が「瓦礫雑考」(1817年)で次のように述べている。
さてかばやきの名も蒲の穂のかたちによりたりといふ証は、大草家料理書に、宇治丸はかばやきの事、丸にあぶりて後に切なり、醤油と酒と交て付るなり、又山椒味噌つけていだしてよきな也、といへるにて、その形をおもひ見るべし。(略)ある人おのが此説を難じていはく、がまの穂をかま鉾といひ、肉羮のそれにかたどりて造れるを直にかまぼこといへれば蒲焼も清てかまやきといふべきを、さいはざるはいかにぞや、かつかまぼこも本はかもじ濁りていひたるなるべし、蒲は濁りてがまといへばなり、さらんにはいよよおかばやきに遠しといへり。こは蒲をがまと濁るが正しきと思へるより、かかるひがこといふなり。凡言のはじめを濁るは古例なし。蒲もすみてかまといへるはかまぼこ即その証なり。蒲原、蒲生などは、今もすみていふ也。又かまをかばといふは、蒲の御曹子などおもふべし、この例は斑をむちとよめると同じ。
鰻丼

文献から鰻料理(蒲焼)をさぐるのは、このぐらいにして、最後に、鰻丼についてふれてみる。蒲焼と鰻丼とは密接な関係がある。鰻丼は蒲焼から派生したものと思われる。宮川政運「俗事百工起源」(1885年)に次のように記してある。
文化年間、堺町の芝居金主であった大久保今助が始祖である。彼は鰻が大好物で、毎日鰻を取り寄せて食べていたが、この当時の蒲焼は冷めないように、温めた糠で保温してあり、食べる時に糠をとるのに大変手数がかかった。そこで彼はこの手数を省く工夫として、温かい飯米を糠のかわりに丼に盛り、その間に蒲焼を入れたところ、蒲焼も冷えず、ごはんも非常にうまかった。これが鰻丼の始まりで、この大久保今助が当時有名人であったので、この方法が大流行し、広く一般に賞味されるようになった。
青葱堂冬圃の「真佐真のかつら」(1857年)には、次のように記されている。市中に鰻めしということを始めたのは、江戸の四谷伝馬町三河屋某の家に勤めていた男が暇(ひま)をとった後、ふきや町の裏長屋で売り始めたのである。それは、この本の著者の幼年時代であり、次第に繁昌した。珍しいと評判になったので、人といっしょに行ってみると、丼飯へ鰻の蒲焼をさしはさんだものであった。わずか価格64文であった。この店は大いに流行したので、皆まねて売ることになったが、価格は年を経て高価になった。
また、別の本には、天明のころ、浜町河岸の大黒屋が始めたともある。いずれの説が先か後かは判明していない。
蒲焼の流行
ところで、江戸時代の初期は建築、中期は服装、末期(安永、天明から文化、文政までの時代をいう)は食物に、それぞれ江戸文化の華が咲いたのである。
江戸文化が建築から服装に重きを置いた時代が過ぎると、食道楽三味の時代になったわけである。初もの(旬(しゅん))を求め、食物はその質、産地を吟味し、珍奇を尊び、高価であることを誇るようになった。それゆえ、江戸文化の中心である江戸に特有の料理が発達したのである。
その中で、独自の美味を誇り、江戸名物の第一にされたものが、鰻の蒲焼である。鰻は古代では塩味で食べていたのであるが、江戸時代までは酢味噌や辛子酢で食べていたのである。
蒲焼としては、室町時代末期、湯づけの本膳に、宇治丸(蒲焼の意。近江の宇治川産の鰻が美味であったから由来した)と汁をそえ、江戸初期の料理書にも、その名が見えるから、このころに整ったのであろう。当時は丸のままあぶってから切り、酒、しょうゆで味をつけ、山椒味噌などを添えて出したのである。
蒲焼は宇治丸からも分かる通り、関西で始まった料理で、江戸の町に鰻屋が多くなったのは江戸中期以降である。中でも、千住尾久の産を売る上野・不忍池の端や店や深川八幡の門前の店が有名で、江戸風の味で作り、金串を使い、大皿に盛って出した。そのころの鰻は、鮨でも蒲焼でも薬効があるとされたが、庶民には駕篭(かご)に乗るのと同じくらい、ぜいたくといわれて値段も高かったのである。
蒲焼の香り
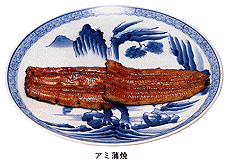
蒲焼の味と香りとは密接な関係があり、その香りは、鰻の表皮粘膜中のピペリジンという物質と、しょうゆ、みりん、魚体油脂などが合わさって、加熱されたときに発生するのである。鰻のヌラヌラを落として焼いては、蒲焼の香りを生じないのである。
蒲焼といっても、次の種類がある。
あみ
いわゆる、ふつうの蒲焼のことで、1尾を開き、横に切ったものを並べて、3本~4本の串に刺したものである。大きさによって、大串(380g以上のもの)、中串(220~250gのもの)、小串(110g程度のもの)の区別がある。
いかだ
細くて小さい鰻を裂いて、横に切らずに、1尾のまま、2尾か3尾を並べて串に刺して焼いたもの。その形がイカダに似ていることからこの名がある。この場合、幅が2cmまでで、3cm以上のものは小串の部類に入れる。細く小さい鰻であるので、油も濃くなくしつっこくないのが特徴で、鰻通(うなぎつう)と称する人たちや婦人に好まれている。天然鰻全盛時の関東では、春と秋に霞が浦で獲れる鰻は、いかだ焼にして好評であった。
しらやき
白焼または素焼をいう。充分に白焼した鰻を蒸して、余分の油分をとり、ワサビ醤油で食べる。
いろいろな鰻料理

鰻料理は調理師の腕次第であり、天然、養成ものを問題にする時代でもないし、現在のの生産量からしても、天然ものは全体の5%以下という現況では、一般消費量の大部分は、養成鰻といっても過言でないのが実状である。
最後に、鰻のうまいところは尻尾であると、古くからいわれている。俗にいわれていることに、魚のうまいところは、年中、よく動いている部分がおいしいとされ、多くの魚では、尾の部分は、むしろまずい部分とされている。
近年、多くの栄養科学者が、鰻の体の各部分の脂肪量を測定して比較した結果によると、体の後部より3/5~4/5の部分の脂肪量が最も多く、頭部と尾端が最少であることが明らかにされ、尻尾の方が脂肪に富んでおいしく、しかもビタミンAが多量であることが証明されたのである。ですから、もし、頭と尾のどちらかを選ぶなら、尾の方を選ぶべきである。最後の鰻が1年中でいちばんうまい時期は初冬である。
土用鰻といわれて、夏が鰻の旬(しゅん)で味覚の優れた時期と思われがちである。これは、食べる側が、暑い夏に体力を消耗して、栄養価のある鰻を身体が要求する。そこで、食べるから、たしかにうまいと感ずるのではないだろうか。
季節的に鰻がうまい時期は、天然ものでは、10月末の下り鰻がよく、養殖鰻は、露地池では、エサを食べなくなる11月以降とされているが、現在のハウス養殖では四季の変化はあまり関係ないといえる。
長い歴史の中で、発達した鰻の料理は、幾多の変遷があったが、鰻の特性を活用し、工夫した調理は、
お造り
鰻は刺身でも食べられる。鰻を裂き、皮を取って薄く切って湯洗いし、冷水でしめる。これを、もみじおろし、青じその葉、ねぎを添えポン酢で食べるか酢味噌で食べる。
あえもの
うざくは鰻を1度焼き、冷ましてから6~7mmに切る。きゅうりのしんを抜き去り、薄切りにして、塩もみして水洗いする。これを3杯酢につけ、きゅうりを添えて盛りつける。
みぞれあえは皮の方から塩でよくしごき、水洗いの後、横に薄く切って湯洗いする。きゅうりを塩洗いした後、かたく絞り、さらに酢で洗い、2杯酢におろし大根を加え鰻ときゅうりを盛りつける。
まきもの
う巻きは鰻の蒲焼を刻んで、しんにして焼きあげた卵焼きである。常に中央に蒲焼がくるように何重にも卵を巻き込むが、絶対に焦げないようにする。
八幡巻きはゴボウの細切りをウナギで巻き、串に刺してタレをつけて、炭火で焼く。京都産の八幡ゴボウを使って作ったところから、この名前がある。冷めたら、輪切りにして、タレをかけて、切り口を見せるように盛りつける。うなぎとゴボウの取り合わせは、江戸時代より相性がいいものとして知られている。
吉原巻きは鰻を裂き、皮を外側にして、湯通ししたウドをしんにして巻き、金串に刺して、とろ火で焼く。2、3回、タレを注ぎかけて焼き、輪切りにして盛りつける。
肝その他
肝焼きは胆のうを除いて、腸はそのままにした内臓を串に刺し、蒲焼用のタレをつけて焼く。
肝しょうが煮は、肝のうを除いた内臓に熱湯を通して、ザルにあげ水気を切る。それを酒としょうゆ同量に浸して、煮汁がなくなるまで煮て、しょうがのせん切りを火からおろす直前に入れる。
中骨の唐揚げは中骨を塩水につけて、すぐに天日で干し、山椒と塩で味つけしてこれを唐揚げにする。
骨せんべいは裂いたままの鰻の骨を、ゆっくりと時間をかけてつけ焼きにして、からからになるまで焼きあげる。
肝吸い

肝をよく水洗いして、薄塩をふり、さっと湯通して、冷ましておく。鰹だしと淡口しょうゆと塩で味をつけたダシを作り、肝と青味野菜を器にもりダシを注ぐ。
煮もの
う雑炊は角切りした白焼きまたは蒲焼と御飯、笹がきゴボウ、ニンジン、モチなどを入れて炊き込み、最後に円形にまんべんなく、卵をとじ込んだもので、白焼きは少し焦げ目のあるものを使う。
半助鍋は鰻の頭を関西では半助といい、地焼の蒲焼の切り落した頭(半助)を、ねぎや豆腐といっしょに煮たもので、関西地方で、流行している。
蒸しもの
せいろ蒸しは地焼の頭と尾を除いた蒲焼、薄焼卵のたんざく切り、タレをまぶした御飯を材料にする。肉が厚くて脂肪の多い鰻を背裂きにして、串を通さずにタレを3、4回つけながら焼く。やや固めに炊いた御飯をしょうゆとみりんたまりを混ぜて熱したタレをかけ、杉のせいろに移して、約20分間で蒸しあげる。そして御飯をほぐし、薄焼を角切りにして、タレをつけて飯の左右に並べる。中央部には、薄焼卵のタンザク切りを並べる。それを蒸し器にかけて、蒸気で3~4分通して作る。せいろはうるし塗りの外箱に、はめ込みひとつずつ、ふたをかぶせて熱が冷めないようにする。
蒲焼のおいしい食べかた
ここで、おいしい蒲焼の食べかたは、お客のよく回転する、いそがしい店を選ぶことである。また蒲焼のうまさを増すものにタレがある。しかも鰻のエキスがたっぷり溶け込んだタレほど、うまさを増すのである。また、蒲焼は温かいうちに食べることが肝要である。冷めてからでは、味が半減する。
そこで、永い経験から生まれた工夫で、鰻を入れる土器の下を湯で温めて出す地方もある。この他、鰻焼立といって、蒲焼を竹の皮に包んで、炊(た)きたての飯の中に入れておく方法もあるくらいである。
蒲焼を食べるのに通ぶる人がある。それは、うまい鰻は天然ものに限るということである。もちろん天然鰻には古くから名産があり、生きた鰻の手ざわりの表現で、織物にたとえていうと、最良の天然ものは、羽二重(はぶたえ)(うすくて、なめらかで、つやのある目のこまかな絹布のこと)であり、2等品は、木綿の手ざわりがするといった。
しかし、現在は天然ものが獲れる河川は汚れ、鰻の好むエサも少なく漁獲量も少ない。
養成鰻の生産技術が発達し、餌料が改善された今日では、優れた養成ものが、天然ものよりも優れ、うまい鰻が生産されているのが現実である。
サンショウ〔山椒(さんしょう)・蜀抄(しょくしょう)〕ミカン科

彫刻家の故朝倉文夫氏が『うなぎ』という本に「鰻公(うなこう)」というタイトルの随筆を寄せられている(1954年)。
その一部分をご紹介してみると――『鰻料理の東京と上方との相違は誰でも知ってのとおりであるが、これが九州になると、又一種の料理方をやっていた記憶がある。鰻だけは他の料理と異り永久に地域的な風味を発揮して存在するのではあるまいか。
東京で上方風をやったり、上方で江戸前をやったりしても決して繁昌するものではあるまい。というのは、鰻は淡水魚といっても温水魚で地域的に気候風土の関係が多分に影響している。九州産は皮膚(かわはだ)が柔く、中国、大阪、名古屋、東京、仙台と北海道に近くなるほど皮膚がかたくなるわけで、この点から大阪あたりまでは所謂上方風料理方でないと風味を損することになる。
筆者は九州、鰻の産地として名高い大野川の辺りに生れたので、50年前東京ではじめて江戸前を丁戴して、こんな柔かなもの、何だか一度腐敗させて焼き直したのじゃないかと口に入れたものを嚥下するのを躊躇して大笑れしたことを思い出す。現在では蒸がどうだとか材料がバチだとか、いささか講釈じみたことをいっているが、ただしかし、鰻茶漬となるとお国振りを思い出す。(中略)
肉を3つ切にして2本の串にさし、臓もつは1本の串、一応焼いたものをタレに浸し又焼く又浸す又焼く、3度位繰り返して串を抜きタレの中に浸しておく。御飯の上にこれをのせて、充分お茶をかける。最初の半分位を呑み干して2度目のお茶で本味になる。これは50年前の田舎料理の記憶で現在果して如何なものかしかし2度目のお茶漬なら戴いてみたいような気もする。(後略)』