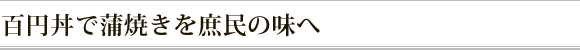戦後の混乱期に蒲焼きを国民へ…
百円丼誕生


中市商店当時の全景

和光ビル建設現場で打ち合わせをする
6代目隆光(右端)
鰻業界が第2次世界大戦を境に一変したように、江戸時代に創業した川魚問屋『中市』も戦後に一大変化をした。
戦前までの『中市』は、東京近辺の川魚商組合に属する、主な天然鰻を扱い、併せて養成鰻も扱う川魚問屋である。この川魚商組合には、およそ20数社の業者が入っており、この組合員は戦後も変わらず営業しており、現在、東京淡水魚卸協組合(山崎勝弘理事長・東京都港区新橋2-20)に所属している組合員(27社)は、ほぼ戦前の顔ぶれと同じである。 戦前、戦後の昭和26年まで、家業の中市を手伝いながら、他の事業に参画してきた6代目田中隆光は、幼少のころから人情家であり、義侠心(ぎきょうしん)に厚く、人一倍に思いやりが強く、鰻一筋に仕事一途の人であった。
そこで、戦後の養鰻業の発展にともない旧来の料理方法と経営方針のままでは、生産過剰になることは明らかである現状を見て、戦前より、若くして、長兄を助けて家業の手伝いをしていた田中隆光は、川魚問屋の仕事上で得た鰻業界の知識と、蒲焼料理店経営の体験をもとに、新たな蒲焼の販売形態と消費拡大を検討した。
当時の日本は、食糧難と戦後復興の発展の兆しが見られる、あわただしい社会情勢であり、誰もが生活に追われ、いそがしく生活していた時代であった。
その頃の日本は日航定期便「もく星」号が三原山噴火口近くに遭難したり、社会情勢不安によるストやデモが各地に起こり、宮城前広場における東京メーデー事件など暗い話題が多かった。明るい話題としては、皇太子殿下立太子の礼、ボクシング界では白井義男が世界フライ級選手権保持者の栄冠をかち得たことぐらいである。
そんな混乱期の食料事情の悪い時代に、6代目隆光は、まず従来の鰻料理屋の形態が、お客さんの注文を受けてから1時間ほど掛けて、食前に出てくる高級お座敷料理であり、当時の蒲焼が200g程度の鰻1尾(1人前として)を裂いて、串打ち、焼き蒸すことが一般的な鰻料理であったことに目を向けた。
確かに、川魚、とくに鰻は生きているものを手早く処理し、料理することがセオリーである。しかし、時間も掛り、能率も悪いこのシステムでは、時代に促さず、生産過剰ぎみの鰻の販路は目に見えている。
次に考えたのが、鰻料理が老舗の専門店であり、高級料理化しているため、食べたくとも、価格の面で、一般国民の口に届くことが遠くなり、年に1回ぐらい食べるのが、ごく普通の家庭の生活事情である。
そんな鰻料理の高級イメージを一般化できないか……。そんな条件を考え合わせて『うまくて安い鰻料理を、広く一般大衆に提供する』という基本方針が固まったところで、この実現に着手努力したのが、『登亭』創業者田中隆光である。

第1登り栄ビル(日本橋宝町)

第2登り栄ビル(登亭神田店)

登亭本社ビル

登亭新橋店

登亭新宿店

登亭銀座店
昭和27年、東京・日本橋室町に
『登亭』を創業

和光ビル(千住仲町)
『登亭』を創業するに当たっての営業方針は安価であること。
この発想は、まず原料である鰻からコストダウンを考えた。永年の川魚問屋での経験から、200g前後の鰻に商品価値が集中している点に注目した。
当時の料理方式からいって100~200gのものが商品として出荷の対象となり、その他のサイズは、1尾を1人前として調理する料理店にとっては、商品扱いせず、値びらきが大きいものであった。
ひと口に、鰻の大小を問わずに蒲焼にするといっても、その調理方法は難しいものである。均一の大きさ(例えば200gのもの)ならば、裂くにしても、焼くにしても、蒸す時間にしても、ひとつの目安がつけば、比較的調理しやすいものである。
そこで6代目隆光は、一流の調理師を集めて、その調理方法の研究に努め、日夜努力を重ねた。
脂肪を抜くために“せいろう”で蒸したり、独得の“たれ”を作ったりして、お客さんの口に合う蒲焼作りに一生懸命であった。もちろん、販売面でも「100円うなどん」と大書きした垂れ幕は、あの芳しい蒲焼の香りに、くっきりと浮き出され、道行く人人を立ちどまらせ、臭覚と味覚を満たし、戦後の復興のエネルギーの一助となる働きをしたのである。
『登亭』の100円どんぶりが好評を得たのは、その価格だけが原因ではない。形にとらわれず、天然物と養殖物の鰻が、どんぶりのふたを開ければ、いっぱいに盛ってあり、しかも、その調理方法は従来の高級料理店と同じ方法で調理するため、味も本格的である。専門店としての格調をくずすことなく、商品の大衆化をはかったのである。
江戸の中心地であった日本橋室町の交差点は、戦後の日本の商業の中心地でもあり早期から深夜まで、足音の絶えない要所でもあった。
そんな商業の中心地に店舗を構えた登亭は、顧客の回転率向上を心掛け、店頭で食事代100円を受け取ると、交換にキップを渡たして、店内にお客さんを送り込んだ。(今では慣習的になっている食券発行も、当時としてはユニークなものであった)。
お客さんの着席と同時に、どんぶりとお茶を配膳できるシステムは、昼食時の1時間で5~6回転をこなすほどであった。つまり、室町の交差点で信号が変わり、登亭の店頭に、その信号が渡ってくる人々のほとんどが店内に入ってくるという状況であった。
おそらく百円丼は、うまさ、ボリュームの点でも、千円ものと変わらない価値感があり、座わると同時に食べられるスピード感が、食糧事情が最悪の時代である背景と重なり、このような反響となったのだろう。
口コミによる宣伝は、何よりも強く、創業者の方針が、問屋時代に学んだ、薄利多売の精神であり、『凧は風が吹かねば上がらない』の例え通り、商売は行動に移すタイミングが大切であり、いったん風が吹いて凧が上がったら、どんどんと高く、大きくさせていき、順風が吹いているうちに、次の時期のことを考え、その対処方法を準備しておくことを心掛けていた。
当時の創業者の言葉に……。
『10階建てのビルでも満杯にできる』と言わしめたほどの盛況で、6代目田中隆光は江戸時代に創業した家業の川魚問屋『中市』を株式会社登亭という企業化を果たしたわけである。
当時の鰻料理の常識では考え及びもつかない鰻に注目し、太さ、大きさを問わず、調理形態も鰻1尾を1人前と考えず、大きいものは3枚に、小さなものは数多く丼に盛る商法は、業界内だけでなく、他の業種の人々にも反響が多かった。
サイズにこだわらない料理形態で、問屋時代に商品価値の薄かった鰻を利用した慧眼(けいがん)は、『うなぎ登亭』を正にうなぎ登りのごとく業績を上げることになった。屋号の『登亭』は、このうなぎ登りから由来したものでる。
原価ギリギリの鰻丼を商品化に成功した『登亭』は更に養鰻生産量の増加が定着化した昭和32年からは“さらに安く”と1人前(たれ・さんしょう付)1串60円という破格値の持ち帰り品(テイクアウト商品)を販売し、養鰻販路拡大の一助を担った。
月1回の特売が、2回となり室町の交差点の道路に、備長炭の火ばちを4台設置し立ち昇る香ばしい油けむりは、多くのお客を集めることとなった。
当初は、開店3~4時間で売り切れ、お客様をお断りするのに骨を折る状況であったが、その後、各セクションも仕事に馴れ予約注文を受けられる様になり、月2回の特売日が定着した。
昭和39年4月に新装10階建ての第一登栄ビルが完成し、正面右側に土産蒲焼コーナーを常設、毎週土曜日を特売日とする様に定着、名物になってきた。

日本橋本店は第1次(4階建て)が昭和27年7月に誕生、その後改築を経て、前述の通り、新装10階建てのビル完成となった。
その間の登亭は、国電新橋駅近くに新橋店が、新宿駅南口には新宿店が誕生している。 第二登栄ビルは、昭和45年5月に神田駅東口前に10階建てのビルが誕生、日本橋室町本店は全館貸ビルとなった。
時の流れが、マイホーム型の家庭サービス重視の傾向から、登亭も商品にそのニーズをくみ入れ、テイクアウト(持ち帰り品)蒲焼弁当の販売作戦へと転換していった。
昭和55年5月に銀座4丁目に銀座店、昭和57年7月に東銀座店も誕生した。
この東銀座店は登録商標である登亭の商号を使わず、登三松の店名で営業している。これはひとつの試みであり、将来の計画のひとつである。
従来の鰻料理専門店を経営し、鰻の大衆化に成功した登亭は、現在有名デパート、スーパーの販売コーナーの形で、31店のテイクアウト商品のみの販売網を持っている。『日本一うまくて安い鰻・登亭』を社訓とした。
この背景には、安定した原材料の確保と安定した価格の維持に心掛け、仕入管理の改善に留意した。つまり、加工鰻の活用や鰻処理の効率化である。
登亭が経営管理面で留意している点は、第1にチェーン化による生産性の上昇である。自社内での鰻処理、調理が専業としてでき、生産性の効率と人件費コストの大きな低減を果たすことが可能である。
その他、自社自体の販売量が著しく上昇するときには、委託加工方式をとっているため、品質管理面も行き届いているので、品質としては、専門店としての位置づけを失っていない。
経営の合理化の達成によって、今日の実績を上げたことが、登亭の鰻に対する一般大衆の信用を保ち、支持されているところである。
また、登亭だけでなく業界全体での課題は、6万トンの消費量がある現在、鰻の人工ふ化が急務であると考える。
今日の日本国民の総人口から考えて、まだまだ国内需要の拡大が可能である。それを目標として、日夜、その達成に努力することが、登亭だけのことでなく、業界全般の発展になることであろう。
女性史研究家で有名な作家の山崎朋子さんが、『食通に献(ささ)げる本』(実業之日本社刊)という6篇の小説と29篇の随筆集の中で、「蒲焼のはなし」というタイトルの随筆を書かれている(1974年)。
その1部分をご紹介してみると……
『何によらず食べることが大好きで、友達から「食べ物の話さえしなければ、もう少ししとやかに見えるのに」と言われるわたしだが、とりわけ好きなものがひとつある。熱の高い風邪のときでも、七転八倒の腹痛のときでも、それさえ食べればぴたりとなおってしまうのだから不思議だ。
そんな有難いものがあるのか、それは一体なんなのか……とあらたまって訊かれると困ってしまうけれど、実はそれはウナギなのである。そしてウナギの蒲焼がわたしの大好物兼守り神みたいになってしまったのは、考えてみると、どうやらわたしが長女を生んだときからであるらしい。(中略)
わたしは、所用があって新宿へ出ると少しくらい歩いてでも登亭へ寄って蒲焼を買って来るけれど、登亭の蒲焼はおいしくて安いのがありがたい。今どき1串2、3百円で売る店……なんてほかにないし、それにウナギが値段のわりに大きいので、あれで損をしないのだろうか……とついつい思ってしまうくらいだ。(中略)
料理の店というと、1品が何百円も何千円もするような店のことばかりが名士の筆にのぼるようだけれど、わたしは、ふところ乏しい庶民でも安心して舌づつみ打てるような店こそ本当にすばらしい店だと思う。新宿の登亭よ、ウナギの店よ、いつまでも健在であれ!』 登亭・新宿店の蒲焼を題材したウナギ讃歌のエッセイである。
日本画家で有名な故鏑木清方氏が『うなぎ』という本に「まんだん」というタイトルの随筆を寄せられている(1954年)。
その一部分をご紹介してみると――
『世界中の美味にこと欠かないという時世でも、私には先ずうまいものを求めるとしたら、まっさきに思いつくのは鰻と天ぷらであろう。
天ぷらのことはさておいて、鰻は昔から養生食いの随一とされ、私などの少年時代にはよそのうちへ行って鰻めしの御馳走になれば、それはもう並々ならぬもてなしを受けたことになるのであった。だから今以ってその観念はぬけきらない。一体東京うまれのものは私だかりでなくそうした傾きが多いようだ。だが私の場合鰻は好きでも一向通人になれない。もちろんこっちの体質への適不適、また食べる時の受入れ態勢といったものの工合で多少の違いはあるとしても、好みをいえば中串どこで筏ならいつでもいい。(中略)こっちの食べる味だけでいえば、先ず前にも云った中串で照りのいい蒲焼のムックリとしたのに箸をつけると身が白く、口を入れれば舌ざわりのトロリと溶け、皮のあとに残らないのがいい、本当の鰻好きは大串を悦ぶのだろうが、私はどうも脂の強いのは向かないので手を出さない。筏というのは多分その形から来ているだろうが、手賀沼あたりのを一番多く食べているらしい。(中略)
穴子の蒲焼もうまいもので、横山町の尾張屋のは名題だけあってうまかったが、うなぎにしても、あなごにしても、私は尾の方を先きに食べる、軽い歯ぎれのよさを楽しむらしい。昔の人は蒲焼の注文に「小粗(こあら)いところ」と好んだのは、今でも落語などに残っている、江戸のことばらしい味であり、またそれが鰻の味でもあるのではなかろうか。』
映画、演劇界でご活躍だった故小林一三氏が『うなぎ』に「うなぎ漫談」という題の随筆の一部分をご紹介してみると(1954年)――
『(前略)大阪では鰻丼の事をまむしと言う。大阪の人は東京の鰻よりも大阪のまむしの方を喜んでいるが、私共東京で育ったものは、大阪の鰻は皮がこわくて今でもまずいと思っている、然し本当に鰻の好きな人はその皮のこわいむしてない鰻の方を喜んでいる様に聞いている。だから私達は本当の鰻好きではないと思っている。ところが先日、東京で東宝の米本君から、一番うまい鰻を食べさして上げましょうかと言うから、蠣殻町辺りの鰻屋で御馳走になった、その時、そこの主人が出て来たので「昔私が学生の頃、金杉橋からお台場の方へ舟へのって遊びに行った時、その時分、鰻かきと言うのが居て、舟にのって棒を持って鰻を取ってるのを見たが今でもありますか」と聞いたら、「今はもう皆養殖の鰻を使って居ります」と言う。「然し昔から聞いているのでは、鰻と言うものは川と海が合する、川口の所のが一番うまいと言うではありませんか」というと、「いいえ、養殖が一番おいしいです。川口の鰻が一番うまいと言うのは、そこでは鰻の食べるものが、一番豊富だから、栄養のいい鰻が居る、という訳で、養殖の方は、さなぎでも何でも、思いのままに栄養を考えられるのですから、いくらでも、うまい鰻が出きる訳です。ただこの養殖の鰻を、水につけておいて、臭味を取ると言うのが、一番難しいところで、つけておく時間や、水のかえ方等に気を配って、一番うまく食べられる時に、料理して御客様に差上げますから、家の鰻はおいしいのです」と説明されるのを聞いて、成る程と感心した。(後略)』